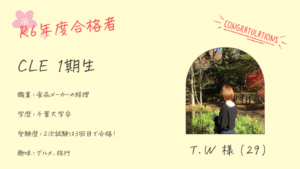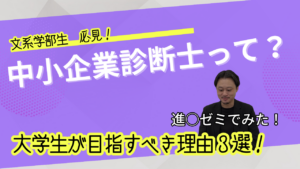R6年度合格答案(52、71、70、69)
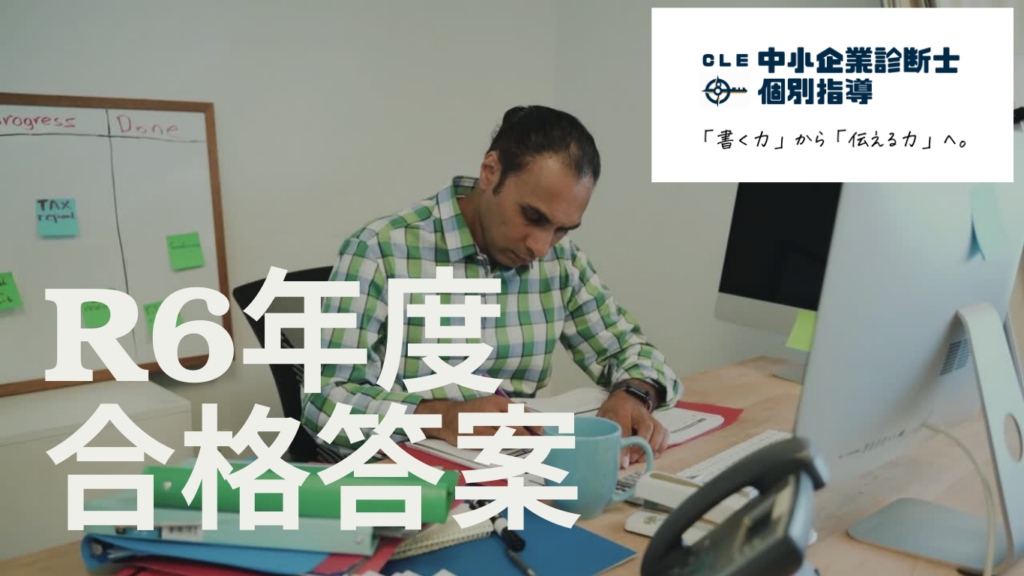
Contents
CLE中小企業診断士個別指導 1期生の合格者、藤本様より「合格答案」が届きましたのでご紹介します!
事例1:52点
第1問
a) 協力会事業者との連携力、地元顧客へのニーズ対応力、自社倉庫。
b) 紙で受注管理が非効率、顧客の新規開拓力不足、地元志向に画一的。
第2問
理由は、従業員の地元志向が強い中、目的を明確化・共有して一体感を醸成し首都圏市場開拓を推進する為。長女任命の狙いは①首都圏開拓に意欲的、大手での経験活用で推進力を上げる事、②管理経験での後継者育成。
第3問
理由は①A社が県内と首都圏に拠点を持ち、②県内事業部が県内の協力会事業者との連携関係を持ち、地元顧客へのニーズ対応力が高くノウハウが蓄積できており、質が高く競合他社と差別化され優位性を持っていた為。
第4問
(設問1)
狙いは①経営幹部を2代目・2代目長男と県内事業部の連結ピンとして機能させ社内の連携を高め、②2代目長男の配置で意思決定迅速化やノウハウ共有を図る事で受託体制強化。
(設問2)
施策は①採用活動で多様な人材を採用しOJT等で教育し、②社員の希望を聞きつつ適材適所な配置をし、③適正な評価制度や成果連動型の賃金制度を導入し、社員の士気向上や組織活性化を図り、顕在する問題を解消する。
事例2:71点
第1問
S カフェスペース併設の自社店舗、X焼を扱う自社ECサイト、3代目のデザイン力とセンス。
W X焼の地位やブランド力が低い、X焼の情報発信不足や販路開拓不足、経営状態悪化傾向。
O X焼の陶磁器祭り、動画の反響等オンラインの有用性、オリジナル食器の提案依頼。
T 一窯元当たりの零細化、百円ショップや外国製陶磁器、高齢化や人口減少が進行中。
第2問
企画は、全国向けに返礼品サイトでX焼で郷土料理を作る実演動画や郷土料理をX焼に盛り付けた写真を掲載した上でX焼とX市の郷土料理をセット販売し、食べたいという感覚や食器の利便性を訴求し、ファン増加を図る。
第3問
食器愛好家に対し、食器の中古販売・買取やレンタルの事業を行い、買取等で食器を捨てなくても良いようにし、季節や料理、顧客の好みのデザインに合わせたX焼で食の楽しみを提供し、愛顧向上で固定客化し売上拡大する。
第4問
施策は①ECサイトを活用して、X焼の拘りや歴史の発信、デザインやニーズの募集等双方向の意識疎通を行い、顧客の声をX焼のデザインに生かすと共に②自社店舗限定のクーポン発行や自社店舗限定商品やイベントの周知をし来店を促し、③実店舗では窯元等との連携でX焼作り等を企画し、愛顧向上で客数や売上の増加を図る。
事例3:70点
第1問
①工場設備レイアウト設計力、②生産性向上に繋がる搬送機器についての提案力、③3つの構造体加工を内製化する事での一貫受託生産体制、④様々な形態対応可能な加工技術力。
第2問
①製缶工程の作業標準化・マニュアル化やOJT教育で他工程の製造要員の多能工化を図り、柔軟な生産体制を構築し製缶工程を強化し、②情報のDB化等で情報を即時共有・反映する事で効率化し、生産能力向上を図る。
第3問
進め方は①生産計画作成を日次化・全社化し、各作業の工数見積りを標準化した上で②生産計画、進捗等生産統制情報、受注・納期情報、部品構成表等をDB化し、③社内で即時共有・活用可能とし、生産統制強化で短納期化。
第4問
事前対策は①定例会や情報のDB化等で営業部と製造部の連携を強化し、製造部の余力や材料の在庫や発注費の現状を把握した社内加工費等の算出で契約金額の精度を上げ、②営業部に研修等を行い製品の訴求力を高め、③技術者同伴での提案体制を整え、交渉円滑化。
第5問
①X社メンテナンスの外注活用等で営業部を営業専任化で営業力を強化し、②顧客ニーズを収集し、ニーズを基に製品設計力を高め、③強みの生産性向上に繋がる提案力や工場設備レイアウト設計力等を訴求し、高付加価値差別化で新規取引先と直接契約し売上拡大する。
事例4:69点
第1問
(設問1)
①有形固定資産回転率 11.26回 ②売上高営業利益率 1.01% ③負債比率 606.94%
(設問2)
特徴は①惣菜事業がテナント出店・業績好調で効率性が高いが、②競争激化で飲食事業の売上が低迷する中、一貫体制の構築・維持のコストや借入金依存で収益性や安全性が低い。
第2問
(設問1)
a)6500 b)240 c)2,670,800 d) X社向けの限界利益=3,000-1,780=1,220円/袋 Y社向けの限界利益=4,800-1,780-1,600=1,420円/袋 Y社向けの1袋当たり直接作業時間=1+1.5=2.5時間 Y社向けの1袋当たり機械運転時間=2+0.5=2.5時間 時間当たりの限界利益を求めると、 X→1,220÷1=1,220円/時間 1,220÷2=610円/時間 Y→1,420÷2.5=568円/時間 よって、X社向けを需要量の6,500袋生産する 機械運転時間の制約より 2.5y=13,600-6,500×2=600 y=600÷2.5=240袋 この時の営業利益=1,220×6,500+1,420+240-5,600,000=2,670,800円
(設問2)
5,912円 Y社向け製品の販売価格をyとすると、 限界利益=y-3,380 Y向け製品を2,400袋生産すると、 直接作業時間=2.5×2,400=6,000時間 直接作業時間=2.5×2,400=6,000時間 余力でX社向け製品を生産すると、機械運転時間の制約より 2x=13,600-6,000=7,600 x=3,800 条件より以下が成り立つ (y-3,380)×2,400+1,220×3,800-5,600,000≧2,670,800 y≧5911.111… よって、5,912円以上
第3問
(設問1)
a)41 b)46
(設問2)
a)-217.17 b) 初年度期首のCF=-540+70=-470万円…⓪ 初年度末のCF=41万円(設問1より)…① 2年度末のCF=46万円(設問1より)…② 3〜9年度末の営業CF=(70-40)×(1-0.3)+40=61万円…③ 9年度末の運転資本の減少額=40万円…④ NPV=⓪+①×0.917+②×0.842+③×5.033×0.547+④×0.460 =-217.17
(設問3)
あるにのみ○
第4問
(設問1)
問題点は①事業間の評価基準に不平等が生じ、コンクリフトが発生する恐れがある事、②上乗せする利潤の適正化が難しい事、③自事業部の利益の追求や短期業績志向となる恐れがある事。
(設問2)
留意点は、事業部長の意思決定ではない投資等は評価対象から外し、事業部長の管理可能な費用を用いた貢献利益で利益責任を明確化。

経営コンサルティングの国内唯一の国家資格:中小企業診断士の資格を保有。CLE中小企業診断士個別指導創業者。
大手レコード会社、日本酒メーカー、税理士法人を経て合同会社CLEMAを設立。公的機関でのコンサルティングや民間企業へのSNS集客・採用支援を得意としている。